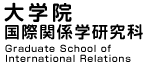在学生の声・修了生の声
在学生の声
研究を通じて日本の文化や社会についても深く理解
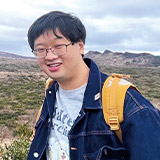
国際関係学専攻
国際政治・開発研究分野
宋 博洋さん
私は中国から来た留学生です。私の研究課題は、冷戦時期における日本の外交政策の変化についての研究です。この研究では、日本が時代とともに変化した外交転換について詳しく調査しています。私は、学校の勉強活動が豊富かつ忙しいという現実に直面していますが、この研究を通じて、日本の外交政策についての洞察を得ることができ、国際関係についてより専門的な知識を磨くことができます。さらに、私は、この研究を通じて、日本の文化や社会についても深く理解することができます。留学生として新しい環境に順応することは大変ですが、学校での学びと研究を通じて、日本という国や文化についての知識や理解を深めることができることを、私たちはとても楽しみにしています。学校には留学生のために専任のカウンセラーがおり、様々なサポートを提供しています。大学では、学生の方々が、自分自身を表現し、知識を深め、国際社会に貢献するためのスキルを身につけることができます。学校は、学生の学問的な成長をサポートするために、最新の教育技術やリソースを提供し、将来的なキャリアに役立つ知識やスキルを身につけることができます。
研究の大きな助けとなる指導・授業

比較文化専攻
アジア文化研究分野
松本 隼佑さん
私は、1917年のロシア革命によって日本にやってきた亡命ロシア人について研究しています。主として彼らのコミュニティ形成のあり方を考察していますが、資料を読み込んでも問題解決の糸口がなかなか見つからない状況が続きました。そこで、研究科での指導・授業が、糸口を見出す大きな助けとなりました。自分の研究テーマについて考え、アウトプットできる授業形態や、他分野の研究を行っている先生・同級生と多角的な視点で議論できる授業環境は、自分の視野を広げさせてくれます。指導教員とも定期的な指導を受けることができるため、研究テーマについて悩んでいるときも相談しやすい環境です。また授業で研究方法や先行研究のまとめ方、資料の扱い方等、今後の社会でも活用できるスキルも学べると思います。同級生と高め合い、多くの知識を吸収できる環境で研究に没頭できることに感謝しつつ、先生方の指導を活かし、研究に邁進していきたいと思います。
- 全て表示
フィールドワークの醍醐味を味わう

国際関係学専攻
国際社会・文化研究分野
石 恩達さん私は中国出身です。新型コロナウイルス感染症の拡大が若者の人生観の形成にどのような影響をもたらしたのかということについて、中国在住の中国人と日本在住の中国人を対象に研究しています。授業で、学部生たちと一緒に地域振興をテーマとしたフィールドワークに参加する機会がありました。それをきっかけに、私はフィールドワークに強い興味を持つようになりました。フィールドワークで重要なのは、調査対象者と信頼関係を築き、具体的な情報を得ることです。私の修士論文の研究では、ライフヒストリー法を用いて15人の生活史を聴き取り、まとめました。彼/彼女たちの語りを整理し、生の営みを構成していくことに調査の醍醐味を感じました。本研究科では、先生方から細やかなご指導を受け、研究方法や論文の書き方等について多くを学ぶことができました。これから社会に出ても、本研究科で得られた経験、知識を生かせると思います。勉学以外では、学生室の職員の方々が留学生の私にとても親切にしてくださいました。手続きのことでわからないことを丁寧に教えてくださいます。このような温かい環境の下で、安心して勉学に励むことができます。
多角的な視野から韓国を学ぶ

比較文化専攻
アジア文化研究分野
野崎 文香さん学部時代に研究対象である韓国に出会いました。隣国について学ぶ面白さを知り、さらに深く研究をしてみたいと思い、大学院への進学を決めました。静岡県立大学での学びや出会いが、私の人生に大きな影響を与えてくれたと感じています。大学院の授業も、毎回が新しい気づきの日々です。各授業では、それぞれの関心事項に沿ったテーマを取り扱っていただけるので、研究対象についてどっぷりとハマることができるのも魅力的です。また、他の分野を研究されている先生方や同級生たちと、各テーマについて議論ができる機会が多いので、自分自身の研究対象に対しても多角的な視点で眺める姿勢が自然とついていくように感じます。知的好奇心が刺激される環境で日々研究ができることに感謝しつつ、これからも研究に精進していきたいと思います。
修了生の声
社会人経験を生かし、正面からフィールドと向き合う

国際関係学専攻
2022年3月修了
専門学校教員
岩本 和大さん
私は社会人学生として3年間、国際関係学研究科に通いました。仕事と研究の両立は大変でしたが、刺激的で充実した日々でした。進学した一番の理由は、仕事を通じてどうしても知りたいことができたからです。私は大学卒業後、国内外の教育現場で異文化に触れながら働きましたが、次第に教育内容だけでなく「異文化接触を通した学びや成長」に関心が集約していき、その先にあったのが大学院進学でした。社会経験を基に研究できるのが社会人学生の良さで、研究成果が次のキャリアと社会貢献につながるのを感じています。授業で最先端の知識を持つ先生方や大学院生同士で語り合ったことは、本当に貴重な時間でした。様々なサポートにも感謝しています。私は国際関係学研究科で学んだことで新たな世界が広がりました。まずは興味のある研究室に連絡を取り、職場等と調整をし、進学の可能性を探ってみるのが良いと思います。
学際的な視野を広げ、比較文学研究への道を開いてくれた修士課程

比較文化専攻
2012年3月修了
常葉大学教員
那須野 絢子さん
大学卒業後、文学研究への憧れを抱きつつも就職の道を選んだ私にとって、社会人として通った国際関係学研究科での時間は、人生に転機をもたらす貴重な経験となりました。限られた時間の中で単位を取得する必要があったため、科目履修生として1年間所属した後に正式に入学をしました。大学時代は、関心のあったイギリス文学に特化した授業のみを受け学士を取得しましたが、静岡県立大学での修士課程では、ドイツ、ラテン、日本の文学、歴史など広い視野を以て学問研究が可能になったことは大きな収穫でした。先生方が私の修論テーマに沿った教材を選定し、丁寧に指導をしてくださった賜物だと思います。現在は、大学院時代の学びを活かし、大学教員として比較文学を専門領域に研究活動に励んでおります。また最近では、オムニバス授業で県立大学において講義を行う機会もいただき、母校に仕事で関われることを大変うれしく感じております。
- 全て表示
「社会」で役立つスキル ―フィールドワークのススメ

国際関係学専攻
2017年3月修了
団体職員
太田 貴さん私は両親が日本とフィリピンの国際結婚(日比国際結婚)ということもあり、大学院では日本人男性とフィリピン人女性の国際結婚をテーマに修士論文を書きました。日比国際結婚に関する論文や書籍をいくつか読んだ際、フィリピン人女性に比べて日本人男性の「声」が少ないことに疑問を抱き、実際に当事者に会って話を聞いて彼らの経験を研究してみようと考えたのがきっかけです。私が注目したのは日本人男性がフィリピン人の妻と出会ってから現在に至るまでの経験で、10名の当事者に聞き取り調査を行って生活史としてまとめました。聞き取り調査で重要なのは相手との信頼関係を築くことです。私は外国人技能実習生と受入企業のお世話をする仕事をしており、実習生や企業の方の相談や要望に対応する時に、調査で身につけた相手と真摯に向き合う姿勢が役に立っています。論文や書籍を読むだけでなく、フィールドに出て自分の目で確かめることも研究の醍醐味でした。
確かな知識・スキルが身につくとともに、貴重な経験が得られました

比較文化専攻
2004年3月修了
MIRAI日本語学校・代表
レイ・ティ・
ホン・ヴィンさん私は1998年10月に私費留学生として静岡に来ました。将来日本語教師になりたいと思い、1年半かけて日本語学校を卒業した後、静岡県立大学で日本語教授法がご専門の水野かほる先生と連絡を取ったところ、「大学院での勉強や研究には日本語能力が不足しており、大学での専攻も希望する大学院での専攻とは異なるため、一年間研究生として入学するように」とアドバイスを頂きました。大学院入学後は、日本語能力が限られていたため苦労しましたが、先生方はそんな私を優しく熱心に指導して下さいました。特に指導教官の水野先生からはいつも温かいお心遣いをいただき、挫折や困難を乗り越える力をいただきました。2002年に日本語教育能力検定試験に合格し、2004年に無事修士課程を修了しました。現在はホーチミンシティで日本語学校を運営し、日本や日本文化が好きで日本語を一生懸命勉強している若者達のために、県立大学で身に付けた知識やスキル、さらに日本で得た貴重な経験を活かすことができるよう頑張っています。
就職先の例
静岡市中学校教員、静岡県高等学校教員、聖隷クリストファー中・高等学校教員、南山学園、A.C.C.国際交流学園、静岡県、藤枝市、静岡新聞社・静岡放送、静岡銀行、中国人民銀行、鈴与システムテクノロジー、サクラクレパス、エンケイ、ハイテクシステム、エコワーク、レマコム、パナソニックフォトライティング久美浜、AFC-HDアムスライフサイエンス、ソミック石川、すずらん協同組合、ボッシュ、プラッツ、源、楽GOO国際、エーツー、さかえ、ヤマハモーターパワープロダクツ、北海道電力、ダイナックス、廣杉計器、トライグループ、日本NCR、金子コード、新大陸、シエスタゲート、アサヒサンクリーン
修士論文題目一覧
- 令和4年度国際関係学専攻
- 外国人非集住地域における多文化共生の地域づくりに向けた行政サービスの提言―静岡県三島市の外国ルーツの子ども支援の視点から―【特定の研究課題についての研究成果】
- 構成主義に基づく中国国連PKOへの関与
- シングルマザーの生活実態と社会的支援に関する社会学的考察―地域におけるシングルマザーの貧困問題の解消に向けて―
- 農民工と格差問題―農村復興への提言―
- 令和4年度比較文化専攻
- 日本人学習者による英語とスペイン語の他動詞の習得
- フランス革命における反革命とその記憶―フランス復古王政期を中心に―
- 中国の非民族自治区におけるエスニックコミュニティの生存戦略―西安市回族の「回坊」を事例として―
- 日本におけるK-POPブームと若者ファンダムに関する研究―女性ファンとソーシャルメディアに注目して―
- 歴史修正主義と記憶の継承―戦後のホロコースト研究から―
- 地方自治体間国際交流の意義と課題―日本・モンゴルの事例を中心として―
- 日本人英語学習者における英語非対格動詞の過剰受動化
- 日本の高校生の語彙学習における指導の影響
- 令和3年度国際関係学専攻
- 日本の外国語系専門学校における多文化共修―接触仮説からの考察―
- 中国の『弾幕』文化の今後―日本の『弾幕』文化との比較をもとに―
- 援助要請行動の抑制要因としての心理的負債の検討―中国人大学生を対象としたweb調査から―
- 障害のパラダイムシフトはいかにして起きたのか―アクセシビリティをめぐる市民社会と政府の相互作用の分析―
- 令和3年度比較文化専攻
- WASTE BANKS IN NEW TOWN: FORMATION OF NEIGHBORHOOD ASSOCIATION AND NEW PUBLIC MANAGEMENT IN INDONESIAN SUBURB
- 日本人英語学習者によるwh移動の制約
- スペイン女性義勇兵の記憶―共和国軍の青いつなぎの女性たち―
- 韓国『#MeToo』運動の展開と拡大要因に関する考察―朴元淳事件を中心に―
- 中国人日本語学習者におけるあいづちの種類と頻度―JSL環境とJFL環境の比較―
- 令和2年度国際関係学専攻
- 中国河北省唐山市住民と在日中国人の人生観の形成と変化についてのライフヒストリー比較研究―新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大時期の事例―
- 中国の対台湾政策―「受動性」の中に見られる「主動性」―
- 中国済寧市における一般市民による健康希求行動の医療多元性についての医療人類学的研究―新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大以降の対策を考える手がかりとして―
- 日中におけるネット上の言語暴力問題の比較分析―なぜネットでは言葉の暴力がよく発生するのか―
- 令和2年度比較文化専攻
- 現代中国における漢服の復興から見る漢服愛好者の共同体意識
- 日本語学習者の読解における助詞「も」の把握に関する一考察
- 日本語学習者の文章産出における文末モダリティの使用実態―コーパスからの考察―
- バリ島の観光村における持続可能な観光開発―3つの観光村を事例とした観光と地域社会に関する研究―
- 令和元年度国際関係学専攻
- EU加盟のコンディショナリティ効果―スロヴァキア政府のハンガリー人政策を中心として―
- 日本における中国人留学生―出身地に着目して―
- 人はなぜフィクションを楽しむのか―「感情規範」という観点から考える―
- 多文化共生時代の防災施策とその実践―静岡市駿河区を事例として―
- 令和元年度比較文化専攻
- カートグラフィックアプローチに基づく日本人英語学習者によるwh疑問文の習得
- 平成30年度国際関係学専攻
- NATOの対黒海政策に及ぼすトルコ=ロシア関係の影響―クリミア併合後の黒海軍事バランスを中心として―
- チョロンにおける華人会館の変容と現状
- 子育て支援に関する日中比較研究―都市中間層家族に関わる乳幼児保育を中心に―
- 平成30年度比較文化専攻
- 中国語を母語とする日本語学習者の役割語の理解
- 日本人英語学習者のbe動詞の過剰般化と過剰使用に関する調査
- 日本語教育における協同学習の効果―語彙授業実践からの分析―
- 現代中国社会における贈与と人間関係―「人情消費」のメカニズム―
- 平成29年度国際関係学専攻
- 大学生のコペアレンティング関係の準備性を高める方策
- 日越断りにおけるポライトネス・ストラテジーの考察―日本人とベトナム人の会社員の比較を通して―
- Actual Life Conditions and Issues of Muslim Women in the Japanese Society
- 平成29年度比較文化専攻
- どのような能力がリスニングとリーディングスキルに影響を与えるのか
- 中国人日本語学習者における第二言語から第一言語への逆行転移―主語省略と目的語省略からの考察―
- 日中両国のインフラ援助に関する比較研究―中国はOECD-DACに加盟すべきか―
- 輸入紅茶から国産紅茶へ―静岡・清水地区の紅茶生産の事例を踏まえて―
- 対人関係を円滑にする丁寧さに関する考察―日本語、英語、ミャンマー語を例として―
- ベトナム仏教乞士派の教義と食―上座仏教の教義と大乗仏教の食の統合―
- 平成28年度国際関係学専攻
- 延辺自治州と北朝鮮の関係―脱北者インタビュー―
- 国際結婚に関する社会学的考察―フィリピン人女性と結婚した日本人男性の生活史から―
- 在日ブラジル人の学業達成―浜松市内における学習支援教室の事例から―
- 中国山東省済南市における回族の宗教生活
- 中国におけるイスラームビジネスの可能性と課題
- 東日本大震災後の被災地における支援物資の分配状況についての研究―宮城県沿岸部と福島県いわき市の事例から―
- 「見えない」華人社会―インドネシア・スマランにおける華人とプリブミの関係について―
- ロシアの「近い外国」政策―ジョージアとウクライナを事例として―
- 平成28年度比較文化専攻
- 世阿弥修羅能の「直ぐ」性について―『通盛』を中心に―
- 大正期における日本の南洋観―東南アジアを中心に―
- 樽井藤吉の思想と行動についての一考察
- 日蘭の国際結婚家庭子女における言語使用実態―コードスイッチングの事例に焦点を当てて―
- 平成27年度国際関係学専攻
- 言語コミュニケーションにおける誤解の考察―在日台湾人と日本人の日常会話を中心に―
- 中国内モンゴル東部の牧畜社会における世帯戦略の変化―通遼市庫倫旗アラション・ソムの事例―
- 中国回族を中心としたムスリム衣装行動の民族誌的研究
- ドイモイの開始以降におけるベトナムの工業化に関する研究―持続的な開発と国有企業の役割―
- 日本の母子家庭における貧困問題と母親の就労
- 平成27年度比較文化専攻
- 越境する家族にみる現代中国人の家族観―在日中国人の事例を中心に―
- 太宰治『津軽』論
- ベトナムにおける2000年以降のメディアの変化―『トイチェ』を事例として―
- Strategic Interaction in English Classes for Japanese High School Students
- 平成26年度国際関係学専攻
- ウクライナ危機の研究―内政と外交のリンケージ―
- コールセンターにおけるストレスとそのマネージメントに関する感情労働観点からの研究
- 地球温暖化防止における排出権取引の現状と課題―中国における排出権取引について―
- 中国西北地区のハラール産業に関する文化人類学的研究
- 中国の大都市部における子育て期の母親のワーク・ライフ・バランスについて―上海に在住する「80後」を中心として―
- 中国の若者によるオタク文化の受容
- 日本女性労働における資金格差の現状と解消策の検討
- 認知症ケアの現状と課題―自己決定を尊重するケアのあり方―
- 平成26年度比較文化専攻
- 第一、第二言語における関係節の処理難度―中国語と日本語の比較―
- 文学作品から見る中国語と日本語のオノマトペの比較―象態詞と擬態語を中心に―
- 「南シナ海における行動規範」の制定をめぐる議論について―中国の選択肢と対応を中心に―
- 平成25年度国際関係学専攻
- インドネシアにおける社会・文化と災害の関係―ジョグジャカルタの火山・噴火の事例から―
- 中国にとっての北朝鮮核問題―北朝鮮をめぐる米中関係―
- 中国の対日関係におけるネット世論の影響―反日デモを例として―
- Political Economy of Capital Controls: A Study of the Chilean and Malaysian Cases
- 平成25年度比較文化専攻
- 内田百閒の研究
- 内モンゴル東部における飲食文化の変容―白い・赤い食べ物から緑の食べ物へ―
- キリシタン版口語文献における主格ガの研究
- 日英語の補文構造の形式と意味
- ヒンドゥー教から仏教へ改宗する人々―ブッダガヤーとガヤーの改宗仏教徒の事例を中心にして―
- 武士の倫理―『葉隠』における知―
- The Acquisition of English Past Tense by Japanese Learners
- Understanding and Designing Emotions in Games: An Evaluation of an Intensive Game Literacy Education Program
- 平成24年度国際関係学専攻
- ジェンダーの視点から日本の自殺問題を考える
- 新中国成立以降、中国大学入試制度の問題点とその原因―日本の入試制度との比較から―
- ストレイン理論の妥当性に関する日中比較研究
- 台湾における脱権威主義の政治過程―蒋経国時代の国家と社会関係を中心とした考察―
- 中国帰国留学生「海帰」の生きる道―2000年代の「新海帰」に注目して―
- 日中テレビ番組の比較研究―バラエティ番組を例として考える―
- 冷戦後の中国外交―パートナーシップをめぐって―
- 平成24年度比較文化専攻
- インドネシアの中のもう1つのヒンドゥー儀礼―トゥングルのカソド儀礼に関する文化人類学的研究―
- 「エリゼ条約の最も美しい子供」―ドイツ・フランス青少年事務所の半世紀―
- 音楽する人びと―ロス・バン・バンと「君が代」の事例から―
- ジャカルタ都市住民「ブタウィ人」の創出と自己認識―アイデンティティ・文化・組織の形成と表象―
- ストリートにおける性愛のポリティクス―LGBTパレードの事例から―
- スリランカの民族紛争と戦争歌に関する文化人類学的研究
- 日・イ経済連携協定に基づくMIDECの事業について―自動車関連事業を中心として―
- 日本語の助詞におけるスリランカ人日本語学習者の誤用について―(主に)シンハラ語の「ta」と日本語の助詞「に」の比較―
- モンゴル語、中国語と日本語の言い間違いの比較研究
- The Core Meaning of the Present Perfect in English
- 平成23年度国際関係学専攻
- 伊東温泉における芸者と地域社会
- 現代若者文化の気分と生活世界―カウンターからオルタナティブへ―
- 在日インドネシア人ムスリムの宗教生活に関する社会学的考察―国際結婚をしているインドネシア人ムスリムへの聞き取り調査に基づいて―
- 在日スリランカ人のライフスタイルと社会・文化上の適応問題―静岡県を中心としたフィールドワーク調査に基づいて―
- 日本とマレーシアの多文化教育―華僑・華人教育の視点から―
- 崩壊国家に順応する人びと―コンゴ民主共和国東部の民族誌的復元―
- Economic Growth, Income Inequality and Poverty Reduction: An Elasticity Analysis of Poverty Reduction
- 平成23年度比較文化専攻
- 英語法助動詞の意味と用法に関する認知言語学的考察―英語教育への応用を目指して―
- 55年体制における民主社会主義政党―その「低迷」と有権者の政治意識(1960-1970)―
- 在日インドネシア人と日本人の国際結婚配偶者における呼称表現―配偶者間での自称詞・対称詞・他称詞の分析―
- 日本語母語話者による英語関係節の習得―難易度の問題をめぐって―
- ファンタジーの誕生―ヴィクトリア朝の人々が描いたユートピア―
- 文様とイコン
- The Acquisition of English Reflexives by Japanese ESL Learners
- 平成22年度国際関係学専攻
- コソヴォ紛争と国際社会
- 在中国日系企業における中国人従業員の文化的企業行動の特質研究―広州地域収集データの分析を通して―
- 在日中国人留学生の異文化適応―「認知」「感情」「行動」の側面から―
- 在日ベトナム人の抱える生活上の適応問題―静岡県在住ベトナム人を中心として―
- 尖閣諸島領有権問題と国際法の機能
- 中国の対韓経済外交の変遷―国交正常化前後の対韓経済関係を中心に―
- 平成22年度比較文化専攻
- 江戸時代における「忠・孝」思想の特徴―主に「忠臣蔵」を例として―
- オルドス・モンゴルの茶の儀礼
- 日本で生活する外国人児童の学校生活におけるコミュニケーション上の課題―コミュニケーション・ストラテジーと語彙ネットワークの調査から―
- 反復と更新―長嶋有と現代文学―
- 「ヒロシマの光」に導かれて―大江健三郎『ヒロシマ・ノート』とその周辺―
- メタファーと関連性理論から見た広告の言葉
- 平成21年度国際関係学専攻
- 欧州安全保障防衛政策の発展とその政策形成過程の分析(2003-2008)
- 中国における若者の恋愛・結婚観―80年代生まれの「一人っ子政策」世代を中心に―
- 日中コミュニケーション行動の文化スキーマ分析
- ブッシュJr.政権時代における対テロ戦争と軍・情報機関の変遷
- ローカル・グッド・ガヴァナンス支援の可能性―サハラ以南アフリカにおけるPCPSとPCECの対比から―
- Comparative Study of European Union's Support for Democratization in Central and Eastern Europe and Eastern Partnership States
- East Asian Economic Development and Division of Labor
- The Quest for Warm-Hearted Aid: How Japan, China and Korea can benefit Africa
- 平成21年度比較文化専攻
- アメリカ黒人女性とブラック・フェミニズム―オプラ・ウィンフリーの仮面―
- 説経節における日本庶民仏教思想の研究―『さんせう太夫』の現代語訳を試みつつ―
- 旅するムスリムイメージ―「鯨の外」で引き受ける応答責任とは―
- 日英語のVoiceの研究―能動-受動、使役-受(け)身の表現形式と機能―
- 福清人ネットワークの変容―福清僑郷とシンガポール福清会館からの視点を中心に―
- 平成20年度国際関係学専攻
- 現代中国における満族の現状と文化の再編
- 公立小学校におけるブラジル人児童が抱える問題分析―文化スキーマ理論の観点から―
- 在日ミャンマー人留学生における自己文化的行動特質と異文化の影響―静岡県在住ミャンマー人留学生を対象とした調査を基に―
- 戦後女子教育における良妻賢母思想の新たな展開―短期大学における教育理念を中心として―
- 多文化組織における異文化間コミュニケーション摩擦―イエメンでのプラント工事を事例に―
- 冷戦の終結と北朝鮮―転換期における北朝鮮の対外政策変化を中心に―
- Cummins仮説の脆弱性の解消に向けて
- 平成20年度比較文化専攻
- 現代韓国における対日歴史認識―教科書記述の問題点を中心に―
- 語用論からみた<笑い>と<自白>―想定の2つの方向性―
- 社会の形成における言語の役割
- 日本語の「~てくる」「~ていく」と中国語の“~来”“~去”の比較対照
- Subjacency Effects under the Minimalist Program: Parametric Values to Grammatical Knowledge
- 平成19年度国際関係学専攻
- オタワプロセスへの評価の再考―「新しい外交」という評価に着目して―
- 平成19年度比較文化専攻
- ウィッテの対華政策1895-1898―借款と鉄道―
- 日本人学習者による英語の代名詞解釈について
- 平成18年度国際関係学専攻
- 再統合的態度とスティグマ付与的態度の源泉―再統合的恥づけ理論の部分的検証―
- 文化スキーマ理論に基づく異文化葛藤への一考察―役割と葛藤原因について―
- 焼津市と静岡市に在住しているブラジル人の子育て方針に関する研究―文化スキーマ理論に基づいた考察―
- 平成18年度比較文化専攻
- 依頼・許可表現の丁寧度と話し手・聞き手の心的距離
- インターネット上における日本人の対韓意識に関する研究―「嫌韓」意識発生構造を中心として―
- ことばと空間―言語における距離化と脱距離化―
- 一八世紀初頭ロシアのオスマン観と対オスマン政策―駐イスタンブル初代大使П.A.トルストイの報告書を中心に―
- 日本語の「シテイル」と韓国語との対応関係―「-ess-」との関連を中心に―
- 平川唯一「カムカム英語」の研究―占領期英会話番組に込められたアメリカ民主主義―
- The Acquisition of Pied-Piping and Preposition Stranding by Japanese EFL Learners
- 平成17年度国際関係学専攻
- <帰国子女>の位置どり―帰国子女イメージと当事者による経験の意味づけ―
- グローバル化の中の地方植物利用―現代日本社会におけるニガウリ受容の事例―
- 日系ブラジル人児童生徒の日本社会への適応について―異文化間コミュニケーションの観点から―
- フランス共和制と地域主義―コルシカの自治要求問題について―
- 平成17年度比較文化専攻
- 谷川俊太郎研究
- 日本語の発話における名詞句の長さと位置の関係について
- 日本における母子の世界―謡曲「隅田川」をてがかりに―
- Death of a Salesman: The American Dream and the Loman Family
- The Acquisition of Bound Variables by Japanese EFL Learners
- 平成16年度国際関係学専攻
- 介助的相互作用の変容と調和―生活介助のフィールドワークから―
- 芸術の有用性―オーストリア文化マネジメントを中心に―
- 少数民族問題解決における国際機関の役割―チェコのズデーテン・ドイツ人問題を事例として―
- 戦後国際秩序の形成とイーデン外交
- 中東地域における大量破壊兵器をめぐる地域秩序―イスラエルの核戦略―
- 米韓同盟に関する研究―冷戦後の米韓同盟と反米運動勃興の影響―
- 平成16年度比較文化専攻
- 近代日本右翼のアジア主義―内田良平を事例として―
- 在日華僑・華人の構成
- 19世紀50年代-60年代における東北アジアの国際関係
- Successive Cyclic Wh-Movement in Second Language Acquisition
- The Acquisition of English Unaccusative Verbs by Japanese L2 Learners
- 平成15年度国際関係学専攻
- 異文化間コミュニケーション摩擦―愛知県・静岡県在住ブラジル人と日本人の非言語コミュニケーションに関する考察―
- 高齢者在宅介護における介護保険制度の介入―コミュニケーションに困難を伴う高齢者の身体をみつめる介護する家族のまなざしから―
- 自衛隊の海外派遣―1987年ペルシャ湾掃海艇派遣問題をめぐって―
- 「障害児の親」の身体介入―形成外科治療のエスノグラフィを通して―
- ロシアの対NATO第二次東方拡大政策―「脅威」認識の変化と9・11効果―
- 平成15年度比較文化専攻
- 越日両言語における人称詞体系とその使用
- 華僑社会における中国文化の伝承―横浜中華街の行事を中心にして―
- 韓国における日本大衆文化受容に対する研究
- 韓国の対日世論形成におけるマスメディアの影響
- A Study of Tennessee Williams's Sweet Bird of Youth: About "Time is Enemy"
- A View of Illusion and Disillusion in the Family Dramas by Eugene O'Neill
- 平成14年度国際関係学専攻
- ドイツ第三帝国における対ユーゴスラヴィア外交
- 東アフリカ牧畜民マサイの植物利用
- 平成14年度比較文化専攻
- 英語における依頼・要請表現の間接性―そこにある距離―
- 韓国人の北朝鮮観―変遷と現在―
- 小林秀雄―「Xへの手紙」を手がかりに―
- 藤樹学成立の思想史的研究
- 夏目漱石の俳句に於ける中国文学の影響
- 蕪村俳句における中国古典の受容に関する一考察
- A Study of Tennessee Williams through A Streetcar Named Desire: Illusion and Reality
- Comprehension of THAT-Trace Effect by Japanese L2 Learners of English
- Semantics of HAVE Constructions: Causation and Experience
- 平成13年度国際関係学専攻
- 在中日系企業における経営上の諸問題―静岡県内企業中国進出の実態調査をふまえて解決策を探る―
- 対中国直接投資の研究ー中国における日系企業の現状と課題ー
- ボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争における停戦交渉および和平案施行過程分析―民族紛争終結における国際社会の介入―
- Financial Crises and Theoretical Models of Financial Crises
- Successful Marketing Strategies in Global Business
- 平成13年度比較文化専攻
- 大野林火研究
- 世俗化・脱政治化に向かう韓国キリスト教会―その背景、変遷をめぐって―
- 平成12年度国際関係学専攻
- 韓国企業の海外進出現況と課題―電気・電子産業を中心に―
- 障害者のアイデンティティポリティクスについて―ディスアビリティ、インペアメント概念再考―
- もう一つの観光としてのグリーン・ツーリズム
- 平成12年度比較文化専攻
- 植民地朝鮮の児童観と方定煥―児童雑誌『オリニ』を中心に―
- 中国の詞と俳句との比較研究
- 道元の『典座教訓』と中国の典座
- Death of a Salesman: Reflections on a Changing Society
- Music and People in Nineteenth-Century England
- Some Triggering Factors for Subjacency among Japanese Learners of English
- The Cultural Politics of the Handelian Oratorio in Eighteenth-Century England
- 平成11年度国際関係学専攻
- 第一次幣原外交期(1924.6-1927.4)の日本の対中外交政策
- 日本、カナダの対中政策の比較一米国要因を中心として一
- ロシア共産党のユダヤ人政策一ユダヤ部局(イェフセクツィヤ)の創設と活動1918-1923―
- 平成11年度比較文化専攻
- アジア華人文化の変容をめぐって
- スポーツとナショナリズムースポーツとナショナリズムの諸相とその相関関係一
- 漱石の俳句研究一中国古典文献の影響について一
- 夏目漱石の研究一少年時代の漢時を中心として一
- 文法化とメタファー的写像―goと「いく」を例として一
- The Immortal Love Songs: Hemingway and his women
- The Still Music of Humanity: Ken Loach's Films and Realism
- 平成10年度国際関係学専攻
- コール政権末期の対EU政策―政権基盤の脆弱化の影響―
- 日韓「安保経協」交渉と日本外交
- EUの共通外交・安全保障政策の有効性と限界―その活動の軌跡を通じて(1993年-1998年)―
- 平成10年度比較文化専攻
- ヴィクトリア朝イギリスにおける茶のイメージ―リスペクタビリティと帝国意識―
- 改革・開放期中国知識界の文化論ー激進-保守をめぐってー
- 韓国社会における「新世代論」研究ー90年代の社会背景を中心としてー
- 地域と言葉に対する意識と使い分けの研究ー青森市在住中高生の調査から一
- 日本語学習者による類義語表現の習得ー「およそ」「ほとんど」「だいたい」「たいてい」の場合ー
- 『葉隠』の思想ー「死ぬ事」の意味ー
- Jane Austen and the Country House
- Verb Movement and Word Order in Tagalog
- 平成9年度国際関係学専攻
- 近代化と広告一大正末から昭和初期における日本社会の変化と広告の役割―
- 少子化と女子労働
- 中国のアフリカ外交1949-1997
- 日韓企業経営システムの比較―韓国企業に移譲可能な日本的経営システム―
- ベルギー連邦制の変遷―言語紛争の解決をめざす新しい連邦制の試み―
- NATO東方拡大を巡る政治過程の分析
- 平成9年度比較文化専攻
- アメリカ人とベースボール―アメリカ社会の「縮図」としてのベースボール―
- インドの貧困がカースト制度から受けている影響
- 象徴語の含意からみた中日文化の相違点―日本語の象徴語をめぐって―
- 多言語国家インドネシアの言語変化状況
- 日本の近代化と北村透谷の思想―日本文化の可能性をめぐって―
- 松尾芭蕉の表現形態研究
- 平成8年度国際関係学専攻
- <アフリカ中心主義>という構築―人種関係をめぐるアイデンティティ・ポリティクス―
- 「開発における女性」の新たな段階―構造調整をめぐる国際女性法上の諸問題―
- 日本人派遣社員の視点から見た中国人従業員―静岡県内対中進出企業の実態調査―
- EU(欧州連合)の第4次拡大をめぐる諸相
- 平成8年度比較文化専攻
- 合衆国における浄土真宗教団の役割一日系社会との関わりについて一
- 韓国仮面劇における道化の研究
- 日本的癒しに関する考察
- パンソリに表出されたハン(恨)の美学と構造の研究
- The Conception of Paradise seen in American Literature: A Study of The Great Gatsby
- The Interpretation of Zibun in Child Language
- "The Leather-Stocking Tales"の今日的意義
- 平成7年度国際関係学専攻
- 海外派遣従業員の配偶者の異文化適応向上にむけて―異文化間コミュニケーション研究と海外派遣人事研究に関する文献調査―
- 北朝鮮の統一政策―その変遷と国力の衰退―
- 青年海外協力隊員の協力活動に関する研究
- レバノン社会における文化の多様性と国民国家意識に関する研究―レバノン社会の鳥瞰図としてのモデル化の試み―
- 平成7年度比較文化専攻
- ジョージ・エリオットとフェミニズム
- 魔女狩りに関する考察―精神と肉体の解放―
- マレーシアにおける華語教育と独立大学運動
- 柳田民俗学における「自己」と「他者」―「米」と「肉」の対照性をめぐって―
- Sur l'absurdité de《La Cantatrice chauve》d'Eugène Ionesco
- 平成6年度国際関係学専攻
- 韓国社会への日本人の適応に関する社会心理学的研究―韓国人によるソーシャル・サポートを中心に―
- 女性に対する暴力撤廃宣言をめぐる法的諸問題―従軍慰安婦問題と旧ユーゴスラヴィアにおける集団レイプを中心に―
- ソ連のアフガニスタン侵攻―対外政策決定の分析―
- 中東ムスリム国家における国家の政治的正統性に関する一考察―アルジェリア、ナショナリズムからイスラミズムへ―
- 平成6年度比較文化専攻
- 雨森芳洲の朝鮮文化認識についての研究
- 東京・新義州間の鉄道敷設とその周囲の群像に関する研究
- 平成5年度国際関係学専攻
- 看護介護分野における国際労働力移動の研究
- 16、17世紀フィリピンの中国人―第一次中国人大虐殺事件の背景・経過・影響をめぐって―
- 1890年前後期における東アジアの国際関係―東アジアの国際秩序における英国巨文島占領事件―
- 平成5年度比較文化専攻
- 鬼の研究―日本の鬼と韓国の鬼神に関する比較研究―
- A Comparative Study of Jane Austen and Conversation Pieces
- The Article System in English and Spanish
- 平成4年度国際関係学専攻
- アメリカ軍政下の朝鮮における国家建設の失敗―信託統治論争を中心に―
- エスニシティの変化と社会的状況の連関に関する研究―日系ブラジル人の実証的分析を通じて―
- 自己組織における組織成員の環境認識と動的適応
- 人道的援助をめぐる国際法―人道的救援権の確立に向けて―
- 中国の対日政策決定の政治的構造―80年代における中日間の諸問題をめぐって―
- 平成4年度比較文化専攻
- 言文一致と写生文の研究