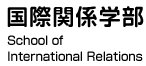新国関の教育デザイン

徹底した少人数教育による問題解決方学習(PBL)を2019年より導入
4つの国関基礎力を鍛え、8つのプログラム専門力を通じて世界と地域社会へ羽ばたく
国際関係学部では2019年度よりカリキュラムを全面刷新しました。
4つの国関基礎力=社会人基礎力にくわえて、
キャリアに通じる8つのプログラム専門力を鍛える新しい実践的教育体系を導入(4+8)
「グローバルかローカルか」ではなく、静岡の地からグローバルな広い視野とローカルな実践力の両方を追求します(G+L)
国公立大学初の国際関係学部30年の地道な蓄積に立ち、グローバル教育の流行を表面的に追うのではなく、
高い水準の学知によって学生の力に即した本当の国際関係学部力を鍛えます。
英語教育ひとつをとっても国際関係学部に適した英語力とは何かを徹底的に考え抜きました。
新カリキュラム4つの特色
1
新カリキュラム4つの特色
教育目標と
キャリアデザインを
明確にしました
国際人としてどのような能力を身につけ、どのような道に進めるのかを明確にしたうえで、基礎4クラスターとキャリアにつながる専門の8ブログラムを組み合わせ、基礎から専門へ無理なく橋渡しします。
2
新カリキュラム4つの特色
1・2年次の基礎教育を
充実させました
1・2年次における基礎教育を担うラーニング・クラスターを新設し、専門課程での学びに必要とされ、社会に出てからも通用する、国際人としての基本的スキルを磨きます。
3
興味関心に応じてさらに自由に学べます
興味関心に応じて
さらに自由に学べます
自由度の高いカリキュラムがこの学部の特色でしたが、新カリキュラムではその自由度をさらに高めました。
4
新カリキュラム4つの特色
問題関心に応じて
深く学べる専門プログラムを
導入しました
国際人としてどのような能力を身につけ、どのような道に進めるのかを明確にしたうえで、基礎4クラスターとキャリアにつながる専門の8ブログラムを組み合わせ、基礎から専門へ無理なく橋渡しします。
4年間の流れ
国際関係学科
貧困、紛争、環境、人権等、地域と地球の問題の解決を探る力を育てる
-
2年次
- 学科別ブリッジ科目2年次には、学科別のブリッジ科目を学ぶことで、自分の興味・関心の幅を広げるとともに、3年次からの専門プログラムにつなげるための基礎を作ります。
- 専門プログラム選択 + ゼミ選択
-
4年次
国際言語文化学科
文化と言語の多様性を理解し、国境を越えて人と人をつなぐ架け橋となり得る力を育てる
-
2年次
- 学科別ブリッジ科目2年次には、学科別のブリッジ科目を学ぶことで、自分の興味・関心の幅を広げるとともに、3年次からの専門プログラムにつなげるための基礎を作ります。
- 専門プログラム選択 + ゼミ選択
-
4年次
Q&A
- Q 国関基礎力とはどのような力ですか
A 国関は国際関係学部を略した呼び名です。国関基礎力とは、アカデミック・リテラシー、英語コミュニケーションカ、 地域実践力、学部基礎力からなり、本学国際関係学部の 学生として共通して身につけてもらいたい基本的な能力 のことです。社会に出て、どんなことをするにしても役に立 つ力でもあります。本学部では、専門的なテ ーマに取り組 む前に、こうした基礎力をきちんと身につけておけるよう なカリキュラムを組んでいます。
- Q PBL Englishとはどんな科目ですか。
A PBLはProject Based Learningの略です。課題解決の作業(プロジェクト)を通して学びを得るというアクティブ・ラーニング(積極的・自発的学習)の手法の一つです。それを英語を使って行うのがPBL Englishという科目です。
英語「を」学ぶのではなく、英語「で」学ぶ。英語を道具として用いることで、本当に使える英語力を身につけることを目指した科目です。英語ネイティブの教員が担当します。 - Q ブリッジ科目って何ですか。
A 国関基礎力を身につけるための科目と専門プログラム科目との間を橋渡し(ブリッジ)すると同時に、同じ学科の異なる専門プログラム間の橋渡しにもなる学科別の科目です。専門プログラムの基礎となる科目や同じ学科の専門プログラムに共通して重要な科目が集まっています。
- Q ブリッジ科目は学科別になっていますが、他学科のブリッジ科目は学べないのですか。
A そんなことはありません。自分の学科のブリッジ科目から最低でも6科目(12単位)を履修する必要がありますが、他学科のブリッジ科目も自由に履修することができますし、履修した単位は卒業に必要な単位として認められます。
- Q 授業は英語で行われますか。
A 英語コミュニケーションカの科目は授業を英語で行うものが多いですが、それ以外の科目は基本的には日本語で授業を行います。中には英語で授業を行う科目もありますが、高度な専門教育は、日本語を使ったほうが学習効果が高いため、おもに日本語で行います。
- Q 専攻する専門プログラムは1つに決める必要があるのですか。
A はい、そうです。専攻する専門プログラムを2年次の終わりに1つ決める必要があります。専攻するプログラムの科目は10科目(20単位)以上を履修する必要があります。
- Q 8つの専門プログラムのどれを専攻してもよいのですか。
A 専攻できる専門プログラムは自分の所属する学科のプログラムだけです。ただし、専攻しないプログラムの科目も自由に履修できますし、他学科の専門プログラムの科目も履修できます。授業で学べる地域やテーマ・問題の多彩さは本学部の大きな特色です。さまざまなことに好奇心を持つのは良いことです。興味・関心の幅を広げて、他学科の専門プログラムの科目もどんどん履修してください。
- Q ゼミとはどのようなものですか。
A ゼミは科目の一つで、正式には演習といいます。指導を受けたいと思う先生を2年次の終わりに1人決めて、3年次・4年次は、その先生の演習を履修します。卒業研究もその先生の指導のもとに進めることになります。ゼミで学ぶ内容は先生の専門分野あるいはそれに近いものになります。ゼミの授業方法は先生によって異なりますが、一般の科目に比べて、学生が自分自身で調べたり、考えたり、議論したりする比重が高くなります。扱うテーマそのものを学生自身が決める場合も多くあります。